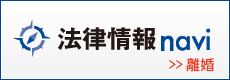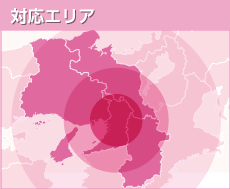いわゆる「養育費・婚姻費用算定表」は実務において広く使われています。算定表は、義務者(多くの場合は夫)と権利者(多くの場合は妻)の年収をもとに養育費もしくは婚姻費用の額を算出するものですが、義務者の年収は2000万円が上限とされています。
ところが、実際には義務者の年収が2000万円を相当程度超えている場合があり、その場合の算定方法につき争われることがあります。
この点につき、東京高裁平成28年9月14日決定が判断していますのでご紹介します。
東京高裁平成28年9月14日決定
事案の概要
1 夫Yと妻Xは、平成3年に婚姻し、長女(平成5年生)及び長男(平成7年生)が出生した。
2 平成26年、YとXは別居し、Yは長男と生活、Xは一人で生活、長女は独立している。
3 XはYに対し、婚姻費用分担調停を申し立てたが、不成立で終了し、審判に移行した。
高裁決定の内容
高裁は次のように判断した。
「2 婚姻費用の算定等
(1) Xは、平成26年に75万4113円の給与収入を得ており、平成27年以降も同程度の収入を得る稼働能力があるものと考えられる。これに収入額に応じた基礎収入率(42%)を乗じて基礎収入を算定すると、31万6727円(小数点以下切捨て。以下、同じ。)となる。
(2) 他方、Yは、平成26年に給与収入として2050万円を得たほか、不動産収入473万9254円及び配当収入1038万円(ただし、いずれも経費を控除した後の所得金額)を得ており、平成27年以降も同程度の収入を得る稼働能力があるものと考えられる。この不動産収入及び配当収入を0.8(1-職業費の割合0.2)で除して給与収入に換算すると1889万9067円となり、Yの給与収入総額は3939万9067円となる。この額は、いわゆる標準算定表(判例タイムズ1111号285頁参照)の義務者の年収の上限額2000万円を大幅に超えていることに鑑み、Yの基礎収入を算定するに当たっては、税金及び社会保険料の実額(1348万9317円)を控除し、さらに、職業費、特別経費及び貯蓄分を控除すべきである。
(3) この点、Xは、収入が増加するほど収入に占める職業費及び特別経費の割合が低下する旨主張する。また、Xは、いわゆる標準算定方式は、年収2000万円以下の者でも一定程度の貯蓄をしていることを前提に制度設計されており、Yについても標準算定方式を準用して基礎収入を算定すれば足りるのであって、平均貯蓄額のような曖昧な概念を持ち出すべきではないとか、貯蓄率の考慮は必須なものではないとか、仮に年収2000万円程度の者の平均的な貯蓄額と年収3900万円程度の者の平均的な貯蓄額との差額を考慮するのであれば、年収1500万円の者の貯蓄率31.7%とそれ以上の年収の者の貯蓄率31.9%との差額である0.2%にとどめるべきであるとかとも主張する。他方で、Yは、標準算定方式は年収2000万円を基準としてそこまでは貯蓄考慮を一律行わないという政策的な取扱いをしているだけであって、これを超える場合には差額にとどめず純粋に貯蓄率を反映させるべきであり、家計調査年報の、総世帯のうち勤労者世帯の貯蓄率が、全収入の平均で21.4%であることからこの割合が控除されるべきであるとか、仮に差額のみを考慮するものとしても、家計調査年報の、二人以上の世帯のうち勤労者世帯の貯蓄率が、年収1500万円以上が31.9%、1500万円未満の各収入の貯蓄率の平均値が16%であることから、その差額の15.9%が控除されるべきであるとかと主張する。
(4) この点、職業費については、Yの場合と年収2000万円以下の場合とでその占める割合が大きく変わるとは考えられないから収入比18.92%とすべきである。他方で、特別経費については、一般に高額所得者の方が収入に占める割合が小さくなり、その分貯蓄や資産形成に回る分が増える傾向にあると考えられる。そして、年収2000万円以下の者でも相応の貯蓄はしているはずであり、Yのこれまでの貯蓄額が判然としない本件事案においては、Yについてのみ純粋に平均的な貯蓄額の満額を控除すべきではなく、標準算定表の上限である年収2000万円程度の者の平均的な貯蓄額との差額のみを考慮すべきである(標準算定方式では、特別経費について年収1500万円以上の者について収入比16.40%との前提に立っているが、年収2000万円程度の場合でも同様の収入比に立っており、この中に貯蓄的要素を既に加味しているともいえる。)。もっとも、本件では、年収2000万円程度の者の貯蓄額と3900万円程度の者の貯蓄額との比較ができる有意な資料がないことから、その差額について推認するほかないところ、Yが引用する家計調査年報の、総世帯のうち勤労者世帯の貯蓄率は、年収1018万円以上が27.3%、全収入の平均が21.4%であること、二人以上の世帯のうち勤労者世帯の貯蓄率が、年収1500万円以上が31.9%、全収入の平均が19.8%であること、その他本件に現れた一切の事情を考慮して、特別経費については年収1500万円以上の者の収入比とされる16.40%とするとともに、Yについて、総収入から税金及び社会保険料を控除した可処分所得の7%分を相当な貯蓄分と定めることとする。
(5) そうすると、職業費及び特別経費の合計額は1391万5750円(3939万9067円×(職業費18.92%+特別経費16.40%))、考慮すべき貯蓄分は181万3682円((3939万9067円-1348万9317円)×0.07)となり、税金及び社会保険料の実額は1348万9317円であるから、これらをYの給与収入総額3939万9067円から控除すると、Yの基礎収入は、1018万0318円となる。
そして、標準算定方式により婚姻費用分担額を算定すると、{(31万6727円+1018万0318円)×100/(100+100+90+90)-31万6727円}÷12≒20万3804円となる。」
コメント
上記の事例では月額20万円とされましたが、夫の年収2000万円、妻の年収75万円である場合、算定表の計算方式に従って計算すると、YからXに支払われる婚姻費用は月額13万円程度になります。
上記高裁決定のように、近時、養育費や婚姻費用の算定につき、極めて精緻な議論が展開されており、専門家でも容易に結論が出せない場合もあります。お困りの場合には専門家にご相談されることをお勧めします。
(弁護士 井上元)