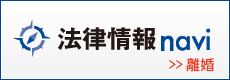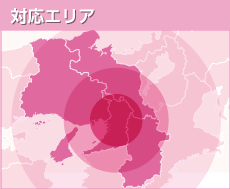婚姻関係が破綻したことについて専ら責任のある配偶者を有責配偶者といいますが、有責配偶者からの離婚請求が認められるか否かという大きな争点があります。有責配偶者の典型例として、妻と子供がありながら不貞をして家から出た夫があげられます。
最高裁判所は、永らく、自己の作り出した破綻を理由として離婚を請求することは許されないとする消極的破綻主義をとってきましたが、昭和62年、有責配偶者からの離婚請求が、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないとする画期的な判断を下しています。
非常に有名な判決ですので、知っている人も多いと思いますが、判決文をじっくりと読んだ人は少ないと思いますので、以下で掲げます。なかなか味わい深い内容ですので、是非ともご一読ください。
最高裁大法廷昭和62年9月2日判決(最高裁判所民事判例集41巻6号1423頁)
1 民法770条は、裁判上の離婚原因を制限的に列挙していた旧民法(昭和22年法律第222号による改正前の明治31年法律第9号。以下同じ。)813条を全面的に改め、1項1号ないし4号において主な離婚原因を具体的に示すとともに、5号において「その他婚姻を継続し難い重大な事由があるとき」との抽象的な事由を掲げたことにより、同項の規定全体としては、離婚原因を相対化したものということができる。また、右770条は、法定の離婚原因がある場合でも離婚の訴えを提起することができない事由を定めていた旧民法814条ないし817条の規定の趣旨の一部を取り入れて、2項において、1項1号ないし4号に基づく離婚請求については右各号所定の事由が認められる場合であつても2項の要件が充足されるときは右請求を棄却することができるとしているにもかかわらず、1項5号に基づく請求についてはかかる制限は及ばないものとしており、2項のほかには、離婚原因に該当する事由があつても離婚請求を排斥することができる場合を具体的に定める規定はない。以上のような民法770条の立法経緯及び規定の文言からみる限り、同条1項5号は、夫婦が婚姻の目的である共同生活を達成しえなくなり、その回復の見込みがなくなった場合には、夫婦の一方は他方に対し訴えにより離婚を請求することができる旨を定めたものと解されるのであつて、同号所定の事由(以下「5号所定の事由」という。)につき責任のある一方の当事者からの離婚請求を許容すべきでないという趣旨までを読みとることはできない。
他方、我が国においては、離婚につき夫婦の意思を尊重する立場から、協議離婚(民法763条)、調停離婚(家事審判法17条)及び審判離婚(同法24条1項)の制度を設けるとともに、相手方配偶者が離婚に同意しない場合について裁判上の離婚の制度を設け、前示のように離婚原因を法定し、これが存在すると認められる場合には、夫婦の一方は他方に対して裁判により離婚を求めうることとしている。このような裁判離婚制度の下において5号所定の事由があるときは当該離婚請求が常に許容されるべきものとすれば、自らその原因となるべき事実を作出した者がそれを自己に有利に利用することを裁判所に承認させ、相手方配偶者の離婚についての意思を全く封ずることとなり、ついには裁判離婚制度を否定するような結果をも招来しかねないのであつて、右のような結果をもたらす離婚請求が許容されるべきでないことはいうまでもない。
2 思うに、婚姻の本質は、両性が永続的な精神的及び肉体的結合を目的として真摯な意思をもって共同生活を営むことにあるから、夫婦の一方又は双方が既に右の意思を確定的に喪失するとともに、夫婦としての共同生活の実体を欠くようになり、その回復の見込みが全くない状態に至つた場合には、当該婚姻は、もはや社会生活上の実質的基礎を失っているものというべきであり、かかる状態においてなお戸籍上だけの婚姻を存続させることは、かえって不自然であるということができよう。しかしながら、離婚は社会的・法的秩序としての婚姻を廃絶するものであるから、離婚請求は、正義・公平の観念、社会的倫理観に反するものであってはならないことは当然であって、この意味で離婚請求は、身分法をも包含する民法全体の指導理念たる信義誠実の原則に照らしても容認されうるものであることを要するものといわなければならない。
3 そこで、5号所定の事由による離婚請求がその事由につき専ら責任のある一方の当事者(以下「有責配偶者」という。)からされた場合において、当該請求が信義誠実の原則に照らして許されるものであるかどうかを判断するに当たつては、有責配偶者の責任の態様・程度を考慮すべきであるが、相手方配偶者の婚姻継続についての意思及び請求者に対する感情、離婚を認めた場合における相手方配偶者の精神的・社会的・経済的状態及び夫婦間の子、殊に未成熟の子の監護・教育・福祉の状況、別居後に形成された生活関係、たとえば夫婦の一方又は双方が既に内縁関係を形成している場合にはその相手方や子らの状況等が斟酌されなければならず、更には、時の経過とともに、これらの諸事情がそれ自体あるいは相互に影響し合って変容し、また、これらの諸事情のもつ社会的意味ないしは社会的評価も変化することを免れないから、時の経過がこれらの諸事情に与える影響も考慮されなければならないのである。
そうであってみれば、有責配偶者からされた離婚請求であつても、夫婦の別居が両当事者の年齢及び同居期間との対比において相当の長期間に及び、その間に未成熟の子が存在しない場合には、相手方配偶者が離婚により精神的・社会的・経済的に極めて苛酷な状態におかれる等離婚請求を認容することが著しく社会正義に反するといえるような特段の事情の認められない限り、当該請求は、有責配偶者からの請求であるとの一事をもって許されないとすることはできないものと解するのが相当である。けだし、右のような場合には、もはや5号所定の事由に係る責任、相手方配偶者の離婚による精神的・社会的状態等は殊更に重視されるべきものでなく、また、相手方配偶者が離婚により被る経済的不利益は、本来、離婚と同時又は離婚後において請求することが認められている財産分与又は慰藉料により解決されるべきものであるからである。」
上記の事案は夫(74歳)が昭和24年にはすでに内縁関係を形成していた者であり、妻(70歳)との別居後36年を経過しているという事案であり、簡単に離婚が認められるわけではありません。
この最判の後の裁判例については、また、おいおいご紹介します。
(弁護士 井上元)