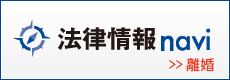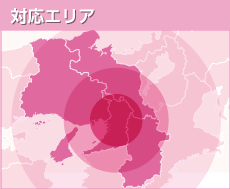嫡出推定と嫡出否認の訴え
民法772条1項で「妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定する。」、2項で「婚姻の成立の日から200日を経過した後又は婚姻の解消若しくは取消しの日から300日以内に生まれた子は、婚姻中に懐胎したものと推定する。」と規定されています。
上記のとおり、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定されますが、実際は、夫の子ではないこともあり得るわけです。この場合、夫が、その子が自分の子でないと主張するためには、嫡出否認の訴えを、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければなりません(民法774条、775条、777条)。夫が、その子との間の父子関係を否定するためには、嫡出否認の訴えを提起しなければならないのです。
このような制度の趣旨は、①家庭の平和を目的とし夫婦間の秘事を公開する不都合を避けること、②法律上の父子関係を早期に安定させること、とされています。
法律上の父子関係が否定されなければ、仮に、その子が自分の子でなくとも、夫は、子の扶養義務を負いますし、子は(母の)夫の相続人となります。
親子関係不存在確認の訴え
しかし、明らかに夫の子でない場合であっても1年の期間経過により、父子関係を覆すことができないとすることには不都合がある場合もあります。
そこで、判例では、民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子であっても、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法774条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができるとしています(最高裁昭和44年5月29日判決、最高裁平成10年8月31日判決、最高裁平成12年3月14日判決)。
事後的にDNA検査により父子関係が否定される場合の問題
上記判例が、「嫡出推定を受けない」と解した事案は、妻が懐胎した時点において、既に夫婦関係の実態が失われていた場合です。
それでは、妻が懐胎した時点において、未だ、夫婦が同居しているなど、夫婦関係の実態が存したところ、事後的にDNA検査により父子関係が存しないことが判明した場合、夫は、「嫡出推定を受けない」として親子関係不存在確認の訴えを提起することができるのでしょうか?
最高裁平成26年7月17日判決(平成24年(受)第1402号事件、平成25年(受)第233号事件)
平成26年7月17日に下された最高裁平成24年(受)第1402号事件判決と最高裁平成25年(受)第233号事件判決は、いずれも、妻が懐胎した時点では夫婦関係の実態が存したところ、事後的にDNA検査により父子関係が存しないことが判明した事案であり、高等裁判所では、共に、親子関係不存在確認の訴えが認められました。
そうしたところ、最高裁は、いずれも、親子関係不存在確認の訴えは認められないと判断しました。以下では、平成24年(受)第1402号事件を掲げますが、平成25年(受)第233号事件もほぼ同様の判示となっています。
第1小法廷の5人の裁判官により審議されたものですが、5人の内2人が補足意見を、2人が反対意見を書いています。
各裁判官の価値観がストレートに表れており、極めて重要なものですので、多数意見、2人の補足意見、2人の反対意見を以下で引用します。
(多数意見)
民法772条により嫡出の推定を受ける子につきその嫡出であることを否認するためには、夫からの嫡出否認の訴えによるべきものとし、かつ、同訴えにつき1年の出訴期間を定めたことは、身分関係の法的安定を保持する上から合理性を有するものということができる(略)。そして、夫と子との間に生物学上の父子関係が認められないことが科学的証拠により明らかであり、かつ、夫と妻が既に離婚して別居し、子が親権者である妻の下で監護されているという事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではないから、上記の事情が存在するからといって、同条による嫡出の推定が及ばなくなるものとはいえず、親子関係不存在確認の訴えをもって当該父子関係の存否を争うことはできないものと解するのが相当である。このように解すると、法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることになるが、同条及び774条から778条までの規定はこのような不一致が生ずることをも容認しているものと解される。
もっとも、民法772条2項所定の期間内に妻が出産した子について、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合には、上記子は実質的には同条の推定を受けない嫡出子に当たるということができるから、同法774条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と上記子との間の父子関係の存否を争うことができると解するのが相当である(略)。しかしながら、本件においては、甲が被上告人を懐胎した時期に上記のような事情があったとは認められず、他に本件訴えの適法性を肯定すべき事情も認められない。
(裁判官櫻井龍子の補足意見)
1 本件では、DNA検査技術の進歩により生物学上の父子関係を科学的かつ客観的に明らかにすることができるようになったという社会状況の変化に応じて、民法772条の嫡出推定が及ぶ範囲について再検討をすべきかどうかが問われている。私は、多数意見に賛同するものであるが、ここに若干の補足意見を述べておきたい。
2 嫡出推定に関する現行民法の規定は、明治31年に施行された旧民法の規定と基本的には変わっておらず、妻が婚姻中に懐胎した子を夫の子と推定し(民法772条1項)、夫において子が嫡出であることを否認するためには、嫡出否認の訴えによらなければならず(同法775条)、この訴えは、夫が子の出生を知った時から1年以内に提起しなければならない(同法777条)とされている。そして、このような嫡出推定に関する規定があることに伴い、父性の推定の重複を回避するための再婚禁止期間の規定(民法733条)及び父を定めることを目的とする訴えの規定(同法773条)が整備されている。
旧民法制定当時は、DNA検査はもちろんのこと、血液型さえも知られておらず、科学的・客観的に生物学上の父子関係を明らかにすることが不可能であったから、これら一連の嫡出推定に関する規定は、そうした状況を前提にして、法律上の父子関係を速やかに確定し、家庭内の事情を公にしないという利益に資するものとして設けられたものと解される。
もっとも、多数意見が引用するその後の当審判例により、民法の嫡出推定の規定の適用について、妻が子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存在する場合に嫡出推定が及ばない例外を解釈により認めるに至っており、いわばバランスをとっているといえよう。
3 近年におけるDNA検査技術の進歩はめざましく、安価に、身体に対する侵襲を伴うこともなく、ほぼ100%の確率で生物学上の親子関係を肯定し、又は否定することができるようになったことは、公知の事実である。
そして、このような状況の中で民法772条の適用範囲をどう考えるかが問われているのであるが、私は、結論としては、父子関係を速やかに確定することにより子の利益を図るという嫡出推定の機能は、現段階でもその重要性が失われておらず、血縁関係のない父子関係であっても、これを法律上の父子関係として覆さないこととすることに一定の意義があると考える。
4 もちろん、DNA検査技術の発達を考慮すると、反対意見が述べる問題意識も十分に理解できるところであり、妻が婚姻中に懐胎した子については、上記当審判例が例外とする場合を除き、嫡出否認の訴え以外によってはいかなる場合であっても父子関係を覆すことができないとすることが相当であるかには、私も疑問を感じないわけではない。特に、子が成長した後、自らの判断で自己の出自を知りたいと願い、あるいは生物学上の父との間での法律上の関係の設定を望んだ場合に、それを実現させる方法がないということについては、その感が深い。
しかしながら、確実に判明する生物学上の親子関係を重視していくという立場もあり得るところではあるが、そのような立場を採ることになると、民法772条の文理からの乖離にとどまらず、嫡出否認の訴え、再婚禁止期間、父を定めることを目的とする訴え等の規定が存在することとの関係をどのように調整するのかという問題に行き当たることになり、解釈論の限界を踏み超えているのではないかと思われる。
親子関係に関する規律は、公の秩序に関わる国の基本的な枠組みに関する問題であり、旧来の規定が社会の実情に沿わないものとなっているというのであれば、その解決は、裁判所において個別の具体的事案の解決として行うのではなく、国民の意識、子の福祉(子がその出自を知ることの利益も含む。)、プライバシー等に関する妻の側の利益、科学技術の進歩や生殖補助医療の進展、DNA検査等の証拠としての取扱い方法、養子制度や相続制度等との調整など諸般の事情を踏まえ、立法政策の問題として検討されるべきであると考える。
(裁判官山浦善樹の補足意見)
1 私は、親子関係不存在確認訴訟において民法772条の嫡出推定が及ぶか否かを検討する場合に、DNA検査の結果生物学上の父子関係がないことが明らかになっていることをどう考えるべきかについて、訴訟法上の問題を中心に意見を補足しておきたい。
2 民法772条は、妻が婚姻中に懐胎した子について、生物学上の父子関係を問うことなく、夫の子であると推定し、子の出生と同時に法律的な父子関係を設定している。もっとも、血縁関係を完全に無視しているわけではなく、一定の要件の下に、嫡出否認の訴え(民法775条)という手続を用意し、夫にその原告適格を認めている。この訴えにおいて生物学上の父子関係の不存在が証明された場合には、法律上の父子関係も子の出生時に遡って存在しなかったものとされる。このように、民法772条は、単なる父子関係の存否という事実についての立証責任分配の規範であることにとどまらず、嫡出否認の訴え以外に父子関係を否定する手段を認めないとする手続法的な規律と相まって、法律上の父子関係を早期に確定するための強力な推定規定となっている。
もっとも、多数意見に引用した判例により、妻の懐胎時において夫婦間に性的関係を持つことがあり得ないことが明らかであるような外観上の事情(例えば、夫が当時刑務所で服役していたなど)がある場合には、嫡出推定が及ばない子として、嫡出否認の訴えによらずとも、親子関係不存在確認訴訟を提起することができるとされている。この訴訟は、出訴期間の制限がなく、確認の利益があれば誰でも提起することができ、また、形成訴訟ではなく、親子関係の存否を確認する趣旨の訴訟であることから、嫡出推定が及んでいない父子関係の存否については、この訴訟によることなく、別訴の前提問題としても主張することが可能であると解される。
妻が婚姻中に懐胎した子に関する親子関係不存在確認訴訟は、上記の外観上の事情が認められる場合に限って例外的に認められるものであって、訴訟の場においては、上記の外観上の事情の存在が認められた場合に初めて血液検査やDNA検査などによる生物学上の父子関係の存否に関する事実の立証の段階に進むことになる(上記の外観上の事情が認められない場合には、親子関係不存在確認に係る訴えは、その段階で却下されることになるのであり、血液検査やDNA検査の結果が証拠として提出されていても意味を持たないことになる。)。
3 これに対して、上記の外観上の事情がなくても、DNA検査等の結果生物学上の父子関係の不存在が明らかである場合には、親子関係不存在確認訴訟の提起を認めるという考え方があるが、これに賛成することはできない。この考え方は、有り体にいえば、外観上夫との性的交渉の余地がない妻が出産した子であることが分かる特殊な場合に限らず、外観上夫婦がそろったごく一般的な家庭に生まれた子であっても、たまたま何かの機会にDNA検査をしたところ生物学上の父子関係がないことが判明した場合は、いつでも、利害関係がありさえすれば誰でも、親子関係不存在確認の訴えを提起して、その不存在を確認する判決を受けることができるというものである。この立場は、法律上の親子は生物学上の血縁だけで結ばれているというに等しいものであり、民法772条の文理やこれまでの累次の当審判例に整合しないものである。
4 また、上記3のように血縁関係を殊更に重視する見解のほかに、①DNA検査等の結果科学的証拠により生物学上の父子関係の不存在が明らかになったことに加えて、②法律上の父との家庭が既に破綻して子の出生の秘密が露わになっている場合、さらに、①及び②の要件に加えて、③生物学上の父との新しい家庭が形成されていること又は生物学上の父との間で法律上の親子関係を確保できる状況にある場合には、親子関係不存在確認訴訟が認められるとする考え方があるが、次のとおり、これらの考え方についても賛成することができない。
②及び③の要件に係る事実の有無の判断基準時は、親子関係不存在確認訴訟の口頭弁論終結時となろう。これらの考え方では、当該口頭弁論終結時に②又は③の要件に係る事実が認められなかった場合には、DNA検査等の結果により生物学上の父子関係の不存在が明らかであったとしても、親子関係不存在確認請求は認められないこととなる。この場合には、DNA検査の結果に含まれる重大なプライバシー情報が訴訟の場に提出され、家庭の平和が害されたという結果のみが残されることになる。
また、上記当審判例に基づく判断においては、妻の懐胎可能時という過去の一定の時点を基準時として上記の外観上の事情が存在していたか否かを判断するのであり、判断の対象となる事実が存在する時点は固定している。しかし、②又は③の要件に係る事実の有無を考慮する考え方は、嫡出推定が及ぶか否かの判断に口頭弁論終結時という将来の不確定な時点における事実の有無を持ち込むものであって、当審判例とはその発想において大きく異なるものである。例えば、夫がDNA検査の結果を前面に押し出して父子関係を否定しようとする場合などを考えてみると、②の要件に係る事実は容易に認定できると思われるが、口頭弁論終結時における②の事実の存否が審理の対象となることにより、当事者が意図的に家庭崩壊を試みる場合もあり得ないわけではない。また、③の要件に係る事実については、評価的要素が多く、その根拠となる事実としては、母と生物学的な父との再婚・同棲や、生物学上の父が判明しその者が子を認知する意思を表明していることなどが挙げられる。しかし、男女の関係は変わり得るものであり、訴訟係属中にも事情は様々に変動し、ようやく口頭弁論終結時において根拠となる事実が認められたとしても、判決後にまた事情が変動しないという保障はない。さらには、親子関係不存在確認請求が一旦退けられた場合に、「前訴では②又は③の事実が認められなかったが、現段階では認められる。」と主張して再訴が繰り返されることを防止する方途も明らかでない。
②及び③の要件に係る事実を考慮する考え方は、いわば法の隙間の中で孤立している子の福祉を実現するための工夫として、その姿勢は評価できるが、上記のとおり子の身分関係を不安定にするなどの大きな問題があり、DNA検査の結果を過大に重視しているように思えてならない。
5 ところで、そこに至る経緯はともあれ、私的にDNA検査が実施されてしまい、その結果生物学上の父子関係が存在しないという事実が既に法廷に現れてしまった以上は、その事実を認め、そこからスタートするほかはないという意見がある。しかし、そのような経緯は偶然に起きたのではなく、先にDNA検査という強力な証拠を得て、これを前面に出せば訴訟の帰すうが有利になるという当事者の意図に基づくものであることもあり、その事実を過大に考慮することにも疑問がある。裁判所が、私的に行われたDNA検査の結果をみて、「生物学上確実な事実が判明した以上は仕方がない」という姿勢をとるならば、DNA検査の結果だけが法廷を支配することになるであろう。
多数意見(補足意見を含む。)も反対意見も、立場は違っても、現在及び将来を視野に入れて、子の福祉を含む家族全体の幸福の実質的な実現を模索していることに変わりはない。同様に、法律上の父、母及び生物学上の父も子の将来を案じ、幸福を念じていると思われる。しかし、特に本件のように、年齢的にみて子の意思を確認することができない段階で、これまで父としての自覚と責任感に基づいて子を育ててきた上告人の意思を無視して、DNA検査の結果に基づき、子の将来を決めてしまうことには躊躇を覚える。とりわけ、法律上の父と母との間においてまだ離婚ないしは婚姻破綻の経緯にまつわる感情的な対立が続いている状態で、子の意思を確認することもなく、その父子関係を決めるのは適切ではないと思う。このような観点からすると、子が、充分に成長して適切な判断力を備えて自己決定権を行使できるようになった後に、自ら父子関係を訴訟において争う機会を設けるということも考えられるが、これは解釈の枠を超えた立法論というべきであろう。
科学技術の進歩に応じ、その効果的な利用が必要であることはいうまでもないが、DNAは人間の尊厳に係る重要な情報であるから決して濫用してはならない。たまたまDNA検査をしてみた結果、ある日突然、それまで存在するものと信頼してきた法律上の父子関係が存在しないことにつながる法解釈を示すことは、夫婦・親子関係の安定を破壊するものとなり、子が生まれたら直ちにDNA検査をしないと生涯にわたって不安定な状態は解消できないことにもなりかねない。このような重要な事項について法解釈で対応できないような新たな規範を作るのであれば、国民の中で十分議論をした上で立法をするほかはない。
(裁判官金築誠志の反対意見)
私は、多数意見と異なり、本件において親子関係不存在確認請求を認めた原判決の結論は相当であり、これを維持すべきものと考える。
1 本件は、妻Aが夫Bとの婚姻中に懐胎した子について、B以外の男性Cがその生物学上の父である確率は99.999998%であるとされているところ、出産から約1年3か月後にAとBは子の親権者をAと定めて協議離婚し、現在ではAは子とともにCと生活しており、子がAを法定代理人としてBに対し親子関係不存在確認の訴えを提起したという事案である。
多数意見は、上記のような事情があっても、子の身分関係の法的安定を保持する必要が当然になくなるものではなく、また、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなど、いわゆる外観説が、民法774条以下の規定にかかわらず、親子関係不存在確認の訴えをもって夫と子との間の父子関係の存否を争うことができるとしている事情も認められないから、本件訴えは不適法であるとする。
したがって、本件の結論を左右するポイントは、法律上の父子関係の確定において血縁をどう位置づけるか、子の福祉の観点から父の確保の問題をどう考えるべきか、嫡出推定を受ける子については外観説が認める場合以外親子関係不存在確認の訴えは一切認められないのかといったことになると思われる。
2 法律上の父子関係が生物学上の父子関係と一致しない場合が生ずることを民法が容認していることは、多数意見の指摘するとおりであるが、民法が生物学上の父子関係をもって本来の父子関係とみていることは、血縁関係の有無が嫡出否認の理由の有無や認知の有効性を決定する事由とされていることからも明らかであろう。
本件において、子はCと生物学上の父子関係を有し、Bとはその関係を有しないことが、証拠上科学的に確実であり、そのことが法廷の場で明らかにされている。しかし、Bから嫡出否認の訴えが提起されなかった結果、また、Bが父子関係の解消に同意しない状況で後述の合意に相当する審判も成立の見込みがないため、もし親子関係不存在確認の訴えが認められないとすれば、Bとの法律上の親子関係を解消することはできず、Cとの間で法律上の実親子関係を成立させることができない。血縁関係のある父が分かっており、その父と生活しているのに、法律上の父はBであるという状態が継続するのである。果たして、これは自然な状態であろうか、安定した関係といえるであろうか。確かに親子は血縁だけの結び付きではないが、本件のように、血縁関係にあり同居している父とそうでない父とが現れている場面においては、通常、前者の父子関係の方が、より安定的、永続的といってよいであろう。子の養育監護という点からみても、本件のような状況にある場合、Bが子の養育監護に実質的に関与することは、事実上困難であろう。また将来、Bの相続問題が起きたとき、Bの他の相続人は、子がCではなくBの実子として相続人となることに、納得できるであろうか。
Cと親子になりたければ、養子縁組をすればよいという意見もあるが、法的な効果に変わりはないとしても、心情的には実子関係と異なるところがあろう。血縁関係のないBとの法律上の父子関係が残るということも、子の生育にとって心理的、感情的な不安定要因を与えることになるのではないだろうか。さらに、Bとの法律上の父子関係が解消されない限り、Cに認知を求めるという方法で、子が自らのイニシアチヴによりCとの法律上の父子関係を構築することはできないのであって、Bに対する親子関係不存在確認の訴えを認めないことは、子から、そうした父を求める権利を奪っているという面があることを軽視すべきでないと思う。それとともに、本件のような場合は、Bとの法律上の父子関係が解消されたとしても、直ちに、Cという父を確保できる状況にあるということもできる。
3 民法が、嫡出推定を受ける子について、原告適格及び提訴期間を厳しく制限した嫡出否認の訴えによるべきこととしている理由は、家庭内の秘密や平穏を保護するとともに、速やかに父子関係を確定して子の保護を図ることにあると解されている。そうすると、夫婦関係が破綻し、子の出生の秘密が露わになっている場合は、前者の保護法益は失われていることになるし、これに加え、子の父を確保するという観点からも親子関係不存在確認の訴えを許容してよいと考えられる状況にもあるならば、嫡出否認制度による厳格な制約を及ぼす実質的な理由は存在しないことになるであろう。
私は、科学的証拠により生物学上の父子関係が否定された場合は、それだけで親子関係不存在確認の訴えを認めてよいとするものではなく、本件のように、夫婦関係が破綻して子の出生の秘密が露わになっており、かつ、生物学上の父との間で法律上の親子関係を確保できる状況にあるという要件を満たす場合に、これを認めようとするものである。嫡出推定・否認制度による父子関係の確定の機能はその分後退することにはなるが、同制度の立法趣旨に実質的に反しない場合に限って例外を認めようというものであって、これにより同制度が空洞化するわけではない。形式的には嫡出推定が及ぶ場合について、実質的な観点を導入することにより、嫡出否認制度の例外を認めるという点では、外観説と異なるものではない。
外観説を超えて、本件のようなケースでの親子関係不存在確認の訴えを認めると、その要件が不明確になるという批判が予想されるが、夫婦関係の破綻は、離婚訴訟において日常的に認定の対象としている要件であり、子の出生の秘密が露わになっていること、生物学上の父との法律上の親子関係を確保できる状況にあるという要件も、とくに不明確ということはないと思う。外観説は、一般的にいえば、夫婦関係の内部に立ち入らずに判断することができ、要件該当性の点でも明確な場合が多いとはいえようが、例えば、最高裁平成7年(オ)第1095号同10年8月31日第二小法廷判決・裁判集民事第189号437頁の事案では、性交渉ないしその機会の有無等をも認定して婚姻の実態の存否を判断しているのであって、こうしたケースでは要件の明確性の差はあまりないといえよう。
親子関係不存在確認の訴えについては、法律上の利害関係のある者であれば誰でも提起できるとされていることが、その適用範囲を広げることに消極的な態度を採る理由とされることも考えられる。人事訴訟である親子関係不存在確認の訴えについて、この点を一般の法律関係不存在確認訴訟と全く同様に考えなければならないかは疑問であって、最高裁平成7年(オ)第2178号同10年8月31日第二小法廷判決・裁判集民事第189号497頁における福田裁判官の意見を傾聴すべきものと考えるが、本件の論点ではないから、立ち入らない。むしろ、本件では、母が子の法定代理人として訴えを提起していることについて、本当に子の利益を考えてのことか疑問を呈する向きがあるかもしれない。その点に疑いがある事案では、子に特別代理人を選任することが適当であろう。そもそもの原因が妻の不倫にあることから、本件親子関係不存在確認の訴えを認めることに躊躇を覚えるということもあるかもしれないが、この点は外観説でも同様であり、父子関係の確定という子がそのアイデンティティの問題として最大の利害関係を持つ事柄について、そういった事柄を訴えの適否に影響させることは相当ではないと思われる。
4 身分法においては、何よりも法的安定性を重んずるべきであり、法の規定からの乖離はできるだけ避けるべきだという意見があることは十分理解できるが、事案の解決の具体的妥当性は裁判の生命であって、本件のようなケースについて、一般的、抽象的な法的安定性の維持を優先させることがよいとは思われない。
家庭裁判所の実務においては、家事事件手続法277条(旧家事審判法23条)の合意に相当する審判により、嫡出推定を否定する方向でこの種の紛争の解決が図られることが少なくなく、外観説の枠に収まらない運用もなされていると紹介する文献もある。このような運用がなされているとすれば、具体的に妥当な解決を図る目的で、嫡出否認制度の厳格さを回避するために生まれた運用ではないかと思われる。本件のような事案の解決においても民法772条により推定される父の意思が決定的に重要であると考えるなら別であるが、そうとは考えられないのであって、このような合意に相当する審判の運用と、本件において親子関係不存在確認の訴えを認めることとの距離は、それほど遠いものではないように思われる。
なお、親子関係不存在確認の訴えが適法とされる場合を広げると、DNA検査の強制や濫用的利用につながるのではないかと危惧する向きもあるようであるが、DNA検査は、現在既に認知訴訟等においてだけではなく、訴訟以外の場面でも広く利用されており、本件のような親子関係不存在確認訴訟を認めるか否かに関わりなく、濫用的利用のおそれは存在している。濫用防止等のために、立法ないし法解釈上一定の規制が必要であるとすれば、それはそれとして検討すべきことであろう。本件において強制や濫用的利用の問題があるわけではなく、DNA検査の結果親子関係の有無が明らかになることは、濫用的利用等がなくとも今後も生じ得るのであるから、本件において親子関係不存在確認の訴えを認めるかどうかの問題とは、切り離して考えるべきであると思う。
(裁判官白木勇の反対意見)
私は、多数意見と異なり、本件において親子関係不存在確認請求を認めた原判決の結論は相当であり、これを維持すべきものとする金築裁判官の意見に賛同するものである。
1 民法の規定は、原則として、血縁のあるところに親子関係を認めようとするものであると考えられるが、法文上は、妻が婚姻中に懐胎した子は、夫の子と推定するとさ(772条1項)、夫の子であるという推定を覆すことができるのは、夫による嫡出否認の訴えによってだけであり、夫以外の何者もこの訴えを提起することができないとされているばかりか、夫による嫡出否認の訴えの提訴可能期間も、子の出生を知った時から1年以内に限るとされている(774条以下)。つまり、制度的には、1年の提訴期間を過ぎると、夫の子でないことが明らかな場合であっても、法的に父子関係を争うことは一切許されないものとされている。
このような制度が設けられた理由として、一つには、家庭の平和を維持する必要があること、二つには、法律上の父子関係を早期に確定させる必要があることなどが指摘されている。その背景には、母子関係は懐胎・分娩という外形的な事実により確認され得るのに対して、父子関係を証明することは極めて困難であるという事情もあったと思われる。
2 しかし、父子間の血縁の存否を明らかにし、それを戸籍の上にも反映させたいと願う人としての心情も法律論として無視できないものがある。そこで、当審判例は、妻がその子を懐胎すべき時期に、既に夫婦が事実上の離婚をして夫婦の実態が失われ、又は遠隔地に居住して、夫婦間に性的関係を持つ機会がなかったことが明らかであるなどの事情が存する場合には、その子は実質的には民法772条1項の父子関係の推定を受けないとしてきた(多数意見の引用する昭和44年5月29日第一小法廷判決以下の3つの最高裁判決参照)。このことは、民法の規定する制度がもはや本来の姿のままでは維持できない事態に至っていることを意味するというべきであろう。
3 近年、科学技術の進歩にはめざましいものがあり、例えばDNAによる個人識別能力は既に究極の域に達したといわれている。検査方法によっては、特定のDNA型が出現する頻度は約4兆7000億人に一人となったとされる。世界の人口は約70億人と推定されるから、確率的には、同一DNA型を持つ人間は地球上に存在しない計算になる。この技術により、父子間の血縁の存否がほとんど誤りなく明らかにできるようになったが、そのようなことは、民法制定当時にはおよそ想定できなかったところであって、父子間の血縁の存否を明らかにし、それを戸籍の上にも反映させたいと願う人情はますます高まりをみせてきているといえよう。
4 以上の事情を踏まえると、民法の規定する嫡出推定の制度ないし仕組みと、真実の父子の血縁関係を戸籍にも反映させたいと願う人情とを適切に調和させることが必要になると考える。その実現は、立法的な手当に待つことが望ましいことはいうまでもないが、日々生起する新たな事態に対処するためには、さしあたって個々の事案ごとに適切妥当な解決策を見出していくことの必要性も否定できないところである。本件においては、夫婦関係が破綻して子の出生の秘密が露わになっており、かつ、血縁関係のある父との間で法律上の親子関係を確保できる状況にあるという点を重視して、子からする親子関係不存在確認の訴えを認めるのが相当であると考えるものである。
コメント
上記の案件は、父子関係とは何か、家族とは何かが問われているものであり、法律解釈を超えて、各人の価値観が強く反映されています。5人の裁判官のうち2人が反対しており、今後、更なる議論が必要だと思われます。
尚、同日の最高裁平成26年7月17日判決(平成26年(オ)226号事件)は、嫡出否認の訴えについて出訴期間を定めた民法777条の規定は,憲法13条、14条1項に違反しないとしているところです。
(弁護士 井上元)